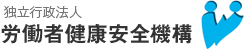医療従事者、産業医スタッフ向け
今月の現場から(保健師コラムリレー)

県内事業場が両立支援に取り組むための支援 ~両立支援規程の作成支援を中心に~
佐賀産業保健総合支援センター 産業保健専門職 田中珠美
佐賀県は九州北西部に位置し、広大な佐賀平野の田園風景と有明海の景色を望むことができる開放的で美しい自然環境に恵まれ、米や佐賀牛、海苔などの高品質な特産品が多くあります。
佐賀県の人口は減少傾向にあり、高齢化率は31.6 %と全国平均(29.3%)を上回るペースで高齢化が進んでいます(令和6年(2024年)10月推計人口)。また、がんや生活習慣病の罹患率・死亡率が全国平均と比較して高い傾向にあります。産業については、地域密着型で「従業員数50人未満」の小規模事業所で働く労働者が全体の63.0%を占めており、全国平均(57.5%)より高い状況です(令和3年(2021年)経済センサス‐活動調査)。このような佐賀県の特徴から、治療と仕事の両立支援(以下「両立支援」という)は、労働者本人はもとより、企業経営においても重要な課題であり、今後の更なる取り組みの必要性を感じています。
佐賀産業保健総合支援センター(以下「さんぽセンター」という)は、事業場が両立支援に取り組むための支援として、事業場へ訪問しての周知と事業場内環境の整備等の助言を行っています。その際は、両立支援に取り組む意義やメリット等を根気強く丁寧に説明していますが、500人以上の従業員を雇用している企業であっても「両立支援を実施しなければならないような従業員は今までおらず、特に必要と思わない」と言われることがあります。その他の事業場でも「対象の従業員が出た時に対応します」「取り組む余裕がありません」などの返答が未だ多いと感じています。
一方で、「以前、がんを患っていた従業員が働いていましたが、どのように対応したらいいのか分かりませんでした。当時、両立支援の取り組みをしていたなら、その従業員は、辞めることなく続けられていたのでは…」と言われた担当者もおられました。
いずれにしても、これまで私が訪問させていただいた多くの事業場では、両立支援のための具体的な取り組みは実施されておらず、両立支援の進め方に関する情報も浸透していない状況にあります。
そこで、事業場が両立支援を導入し易くするため、支援の申し込みを頂いた事業場には、参考文献1)をもとに作成した両立支援規程(以下「規程」という)のひな形をお渡ししています。その後、社会保険労務士(社労士)の資格を有するさんぽセンターの促進員と私(保健師)の2人体制で訪問し、当該事情場の就業規則と照らし合わせながら、事業場の実態に沿った規程作成支援をしています。ひな形自体も、規程をより運用しやすいものにするため、必要に応じて加筆修正しています。事業場担当者は、規程作成に携わる過程で、両立支援に対する理解を深められているように感じます。
以前、事業場から、難病をかかえる従業員への両立支援に関する相談がありました。その後、担当者から「この規程を作成するきっかけとなった従業員は、無事に骨髄移植を行い、復職しました。ご家族にも安心していただけたので、本当に両立支援に取り組んで良かったです」とご報告をいただきました。事業場が両立支援の意義を理解されて実際に取組まれた結果、従業員がスムーズに復職されたことを大変嬉しく思いました。
今後も保健師や社労士それぞれの専門性を高めるとともに、職種間の連携を強化し、県内事業場の支援ニーズに応じた質の高い支援を実施することを心がけていきたいと思います。
1)遠藤源樹編著 がん患者就労支援ネットワーク著 小島健一監修『選択制 がん罹患社員用就業規則標準フォーマット がん時代の働き方改革』 労働新聞社 2019年